心の不調を感じたら3つを軸に選ぶ
別記事でうつ病の簡易診断を書きましたが、今回はその続きです。
自分がうつ病もしくは気分障害などの疑いがあるかもというとき、パッと思いつくのが診療内科やメンタルクリニック、精神科ではないでしょうか。
今まで診療内科に行ったことがない人が大半だと思いますので、診療内科の選び方についてうつ病生活中の筆者がクリニック選びでのポイントを解説します。
おさえるべきは以下の3つです。
- 先生との相性が良いか
- 診察料、文書作成料が明確か
- 公共機関を使って通えるか
順に説明します。
1.先生との相性が良いか
まず先生との相性です。
実はわたし、うつ病の診断を1ヶ月で2回受けました 笑)
1回目の診断は電話して即予約がとれたクリニック
前回の記事でうつ病の簡易診断を見事にパスしていた私は、口下手なこともあり症状を箇条書きにして持って行くとすぐにうつ病の診断がおりました。
精神的にまいっていたので、うつ病の診断がおりたときはホッとしました。
こんなことで病気と言っちゃっていいの?と思ってたので、肯定されたようなホッとした気持ちになりました。
・・ただ1回目の診断の先生はどこか高圧的で「こうしてください」感が強い先生でした。
治療は先生との対話と薬物療法が主になるため、この先生と会うのは嫌だな~と思うとそれだけでストレス!途中で治療を断念しかねない。
2回目の診断は電話をして1ヶ月以上予約がいっぱいのクリニック
2回目のクリニックは最初に電話をかけていたのですが1ヶ月以上予約がいっぱい・・
予約がとれるようになったらクリニックから電話がくる形でした。
それでも良いと返答し、実際に電話が来て受診できたのは1ヶ月半後でした。
症状を箇条書きにしていたこともあり、2回目のクリニックでもうつ病の診断をもらえました。
先生との相性は人それぞれですが、2回目の先生は「あなたの望みを基本として・・・」というスタンスの先生でしたのでとても安心できました。
うつ病や気分障害といった病気は長期戦です。
診断をもらった後に傷病手当金の申請に繋がっていきますが、先生の診断書が毎回かならず必要になりこちらの意向をしっかりと反映してくれる先生が重要になってきます。
今後のためにも先生との相性はもっとも大事にしたほうが良いです。
2.診察料、文書作成料が明確か
うつ病や気分障害の治療は長期戦です。
症状や段階によって短くて1週間に1回、長くて1ヶ月に1回の頻度で通院が必要になります。
休養必須で傷病手当金等の生活になった場合に、いくら受給できていくら支出があるのかの見込みは生活のうえで大事な試算です。
傷病手当金生活の場合、診察料とは別で手当金の療養担当者記入欄の文書作成を先生に頼むことになるのでホームページなどでおおよその料金を確認しておきましょう。
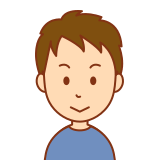
相場としては・・
健康保険の3割負担でお薬代込みで2,000円~3,000円
傷病手当金の療養担当者用紙の文書作成料で2,000円前後
市により異なりますが「自立支援医療」という厚労省の制度があります。
年収によってですが医療費が軽くなる制度ですので該当する方は申請することにより医療費が補助されます。
3.公共機関を使って通えるか
繰り返しになりますが、うつ病や気分障害の治療は長期戦です。
できれば車を使っての通院はオススメしません。
治療が長期化した場合、傷病手当金のお世話になると思いますが傷病手当金の支給はざっくり月収の2/3です(期間は通算1年6ヶ月が上限)
失業手当では月収の50~80% (期間は年齢、在職期間により90日~330日)
つまり、いままでと同じ生活はできません。
車ありきの生活は家計を圧迫する大きな固定費です。
また、公共機関での通院であれば通院費として医療費控除の対象となります。
私は2台ある車の通勤用だった軽自動車を手放し固定費を大幅に削減しました。
傷病手当金や失業手当が支給されても貯金がだんだん減っていくのは大きなストレスになります。
これを期に家計を見直すことをオススメします。
今後、家計節約術などもアップしていきますので参考にしてもらえると幸いです。
文中のうつ病の簡易診断については下記で書きましたので見てみてください。
症状の箇条書きの書き方は相談にのります。Contactからどうぞ(記事も書きたいと思っています)
記事を読んでくださりありがとうございます。



コメント